労働法 第9日目 社員への損害賠償請求
今回はちょっと変化球。損害賠償のお話です。仕事を行っていく中で、会社に損害を与えた社員がいる。その社員に損害賠償を請求したい、またはその額を給与天引きしたい、などなど、まあありますよね。そういうこと。車や物品の破損などは、わかりやすい損害かと思います。
で、下記のような条文があります。
労働基準法 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
はい、何だか損害賠償請求してはいけないような雰囲気ですね。しかし、よく見てみましょう。この条文で言っているのは、あくまで「額を予定してはならない」ということです。つまり、実際に損害が起こる前に、労働契約の中に「〇〇のような場合は、××円を支払ってもらう」というような、金額を予定しておくことがいけないわけなんですね。そして、実際に被った損害について、就業規則などに「損害賠償を請求することがある」という記載をすること自体は、特に問題がないわけであります。そして、実際に損害が生じたときに、賠償請求をすることも何ら問題がありません。このことは、下記通達でも明らかにされています。
S22.9.13 発基17号 本条は、金額を予定することを禁止するのであつて、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。
では、実損額をそのまま損害賠償請求してしまってもいいのでしょうか?社用車を大破させた、高額の現金を逸失した、悪いのは労働者なんだから全額請求しちゃえ(^-^)と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的に見て労働者に全額を負担させることはまずできません。
例えば交通事故であれば、過重労働や安全教育の不備等、会社の責任が全くないとは言い切れないからです。裁判例を見ますと、損害額の2~3割が限界ではないかと一般的には言われています。この辺りは民事上の問題となりますから、請求額について不安がある場合は顧問弁護士等に相談した方がいいでしょう。
損害賠償を給与天引きできるか
損害賠償請求できるとして、その額を給与から天引きできるかという問題もあります。原則として、これはまずできません。下記の規定があるからです。
労働基準法 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
これを、「賃金全額払いの原則」といいます。給与は全額支払わなければいけないのが原則で、社会保険料など法令で定められたものや、労働組合費など労使協定によって定められたもの以外は天引きできません。よって、損害賠償については、給与天引きできないことになります。
厳密には、労働者の合意による給与との相殺であれば、この原則に反せず適法であるとした判例もあります(日新製鋼事件最高裁判決 H2.11.26)。しかし、あくまで労働者の自由な意思に基づく同意であることが前提でありまして、「会社側が同意を強要した」と判断されないためのハードルはかなり高くなっております。事実上、損害賠償の給与天引きはできないものとして、別途労働者に請求書を渡す業務フローが望ましいと言えるでしょう。
違約金とは?
条文では、損害賠償の前に「違約金」とありますね。違約金を定めることはできませんと。違約金とは、例えば短期間で転職した場合などに、本人や身元保証人に対して要求する金銭のことをいいます。会社としては、採用・研修等のコストをかけているわけですから、すぐに転職されてしまうことに、納得がいかないことも理解できます。ですが、このような違約金を定めることは違法ということです。退職の自由を奪ってしまうことに繋がるからです。
短期間での転職に違約金を定めることはできませんが、では次の場合はどうでしょう。
研修の費用を会社が支出しました。その研修終了後の5年間は必ず当社で勤務してください。5年経過前に退職した場合は研修費用を会社に全額払ってもらいます。
これは、違約金または損害賠償額の予定と考えられる可能性があります。可能性、つまり適法とされる場合もあるわけですが、その分かれ目はどこなのでしょう。
①業務の一環かどうかと、拘束期間
業務命令であれば、実質的に退職の自由を奪ってしまうと解釈されますので、違法性があるといえます。たとえ、業務に役立つ資格取得のための研修であっても、業務の一環として受講させたのであれば、その後一定期間の間に退職した場合の費用返還を求めることはできません。
自主参加であれば、実費分を返還してもらう条項を設けることについて、退職を拘束する期間が短期間であれば問題ないとした裁判例もあります(藤野金属工業事件 大阪地裁 S43.2.28)。短期間というのは曖昧ですが、この裁判では1年間でした。例のような「5年間」の勤務を要件とすることは認められない可能性もありますので、注意が必要です。
②金銭貸借契約であるかどうか
看護師のお礼奉公問題について考えてみます。お礼奉公とは、看護学校の費用等について、奨学金のように援助する代わりに、卒業後の一定期間を勤務した場合は返済を免除するというものです。一定期間を経過する前に退職した場合は、一括返済(もしくは分割)を求められることになります。現実に多く行われていることですが、適法なのでしょうか。実は様々な解釈があり、裁判例を見ても「返還義務はあるが全額は必要ない」「あくまで紳士協定に過ぎず、法的拘束力がない」など事例によって判断が分かれています。
ただ、確実に言えるのは、「奨学金を盾に退職させてもらえない」場合や、労働契約の中身に「〇年間勤務しなかった場合は、全額を返還しなければならない」と規定する場合は、前述の労働基準法第16条違反となるでしょう。
これに対し、「金銭貸借契約」として、労働者に返済義務を課し、一定期間労働した場合にはその返済義務を免除するとなっている場合は、適法です(労働法コンメンタール)。お礼奉公のような制度がある企業は、一度どのような契約であるかを再確認しておくと、トラブルになった際に対処がしやすくなるといえます。
本日もお疲れ様でした。
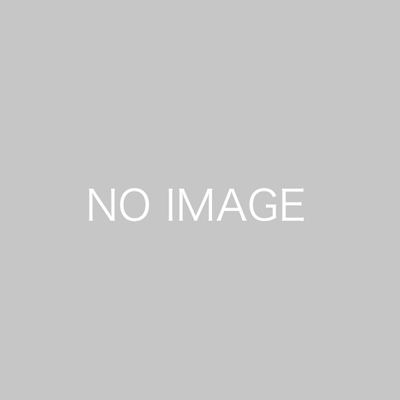



.jpg)
.jpg)
.jpg)

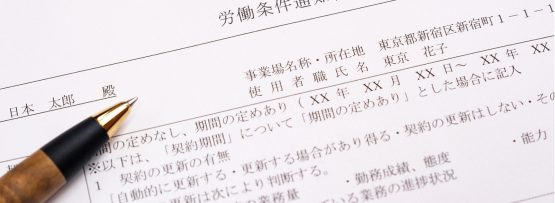



















この記事へのコメントはありません。